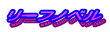


浩子は夜10時頃窓外を見つめることが好きであった。特に秋から冬にかけて、
冷たい空気がひっそりと闇にまぎれているのを見ていると自分の心も澄んでいく
ように思えた。それはある種の心地よさを感じた。ファミリーレストランやコン
ビニの明かりが24時間遠くに輝いて見えるときは何故か安心感を覚え、今の自
分に生きる力を与えてくれているようにも思えた。
浩子は自らの不倫が原因で3年前離婚した。別れた夫との間に男の子が一人い
た。既に中学生になったはずである。別れるときの条件は子供を夫の下において
いくことであった。夫は寡黙で浩子への愛情を言葉で示すタイプではなかった。
その頃の浩子は何か物足りなさを感じていた。別れ話になったとき夫は
「君に息子は育てられない」
と今まで聞いたことのない強い口調で、息子を渡そうとはしなかった。庭に咲い
た牡丹の花をむしりとるような夫の激しさを初めて垣間見る別れとなった。
自分らしく、自由に生きたいと思う浩子には、かねがね優しく包んでくれる男
性、林がいた。浩子は林との人生は雑誌などに掲載されるおしゃれな夫婦になれ
そうだと思えた。林は
「僕の陶芸を理解してくれる浩ちゃんが僕のところに来るなら僕は大歓迎だよ」
と常々笑いながら言っていたので家を出る決心がついたのであった。浩子は林と
の生活を始めたが、数ヶ月すると個展に出品する陶芸製作だと証して林は帰宅し
なくなった。やがて何の連絡もないまま、浩子の留守の間に林の荷物は無くなっ
ていた。
林は浩子との恋ゲームを楽しみ、恋の危うさが醸し出す酔いが心地よかったの
であろう。
ゲームは終わったのである。浩子は林との終わりを理解し始めると何故か無性に
林の笑い声が耳底に蘇った。その笑いは『言葉遊びで恋ゲーム恋ゲーム』と歌っ
ているように思えた。一人の女性に縛られたくない林の生活スタンスを見抜けな
かった自分の愚さに気づいた。林は遊び感覚であっても浩子にとって家庭を壊し
てしまった代償を考えると息苦しかった。
浩子の噂は職場中広がり好奇な目で見られたが、全てを忘れるようにこの三年
間ひたすら働いてきた。どんな自由な日々を過ごしても分かちあえない空しさは、
部屋の隅に転がっている埃まみれの砂時計ようなものであった。好きなワインを
飲んで涙で心を浄化しようとてみたが自分の心の寒さは募るばかりであった。甘
い言葉ひとついわない夫が子供を必死に守ろうとしたあの別れのときの姿を浩子
は思い出した。失って分かる本物のやさしさを感じるたびに、浩子の心は古傷の
ように哀しく疼いていた。
激しく生きることも、穏やかに生きることも、人間終るときはそう大差がない
とこの頃思うようになってきた。
一日が終ろうとするときは子供への懐かしさで胸がいっぱいになった。会えな
い辛さよりも息子への懐かしさを持てる幸せを噛み締めようと自分に言い聞かせ
てきた。友達の久美子は家に来ると
「あなたはお金と自由があるからいいわね。私なんか何時自分の楽しみが出来る
か分からなわよ。自分のために買う洋服はバーゲンで、子供の学資の仕送りのた
めに働いているようなものよ」
「うらやましいわ」と浩子が言うと
「離婚なんて今、いっぱいある話よ。バツ2だってあるのよ。振り返らず楽しん
だ方がいいんじゃない。私だって、家から出たいと思うことはあったわよ。いつ
か子供は独立し私だって一人になるわよ。浩子はストイックに考えすぎよ」
「そうかなあ」
と浩子は答えたが心の中では久美子に羨ましさを感じていた。
浩子は何も考えず就寝しようとしていた。携帯電話が鳴った。浩子が手にする
と相手は無言のまま、やがて切れた。
数日後、突然夫が訪ねてきた。二人は眼を合わせず向きあい、浩子はただ深々
と頭を下げすすり泣いた。夫は視線を落としたまま絞り出すような声で
「秀樹が待ってるよ。家に帰ろう」
とだけ言った。夫の苦しさと浩子の辛さは霙降る坂道を濡れ鼠になって登るに似
ていた。
玄関の扉は終わりのないドラマのように開き、冬の残照はその扉越しを澄んだ色
で照らしていた。

