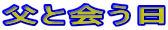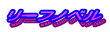
孝太が学校から帰ったあの日、母が涙を拭いているのを見た。その頃から家の
空気が変わりだし、父の帰りが遅いことに気づいた。家族の会話がなくなり、夜
半になると両親の諍(いさか)いをする声が孝太の部屋まで聞こえた。孝太は無
性に悲しく不安感に包まれ、これは夢であって欲しいと願った。
願いもむなしく両親が離婚したのは、それから数ヶ月後の、孝太が小学三年生
になった春のことだった。父とは一月に一度会うことになり、約束の日が来るの
を孝太は楽しみにしていたが、中学生になると、両親双方の気持ちを察するよう
になっている自分に気づきだした。
父と会うある日のことである。勉強部屋の窓から外を見ると、冬の枯れ木が風
に揺れていた。孝太の複雑な心に比べ静かな風景だと思った。
「時間でしょ。間に合うの?送っていってあげようか」
母が言った。
「いいよ。どうせあの人、時間どおりに来ないから」
さも面倒くさそうに答えた。父と会うことが煩わしいとでもいうような声だった。
「じゃあ母さん仕事に行くわね」
玄関のドアが閉まった。孝太はなぜかほっとした。その瞬間父の顔が浮かんだ。
孝太は父との再会を楽しみにしていたのだ。母にはねだれないものでも父には頼
めたからである。父と会う場所はいつも孝太が決めていた。中学になった今では
友達がめったに行かないような場所を考え、その日は旧道に沿った蕎麦屋を選ん
だ。
店に入ると父は既に来ていた。孝太の顔を見るとうれしそうに手を上げた。孝
太は店内をすばやく見回し中学生がいないのを確認しながら父のテーブルに近づ
いた。
「元気か。好きなものをとっていいよ」
とメニューを広げた。父は孝太の姿を隅々まで見ているようだった。
「父さん、元気」
「ああ元気だよ。会社がこの頃忙しくて、帰りが遅いんだ。家族に迷惑をかけてい
るよ」
家族と言う言葉が孝太の頭を混乱させた。自分はもう家族ではないのか。母には聞
かせたくない言葉だった。自分も父の背景にある生活を聞きたくないと思った。逆
に母のことを聞いて欲しいと心の中で思った。
「部活はどうだ?父さんも中学のときは剣道をやっていたんだよ」
「父さん、段、取った?」
「うん 取った。高校でやめてしまったがなあ」
運ばれてきたエビフライやカツフライは揚げたてでおいしそうだった。
「冷めないうちにおあがり」
父はビールを飲みながら言った。
父は、自分が他の女性に走り、ひとつの家庭を壊してしまったことを息子に、会
う度に、詫びたい思いに駆られていた。押し黙って向かい合っている二人の間に
は、渡れない川があるようだった。孝太を見つめていた父はいきなり言った。
「子供は宝だなあ」
それを聞いた孝太は、顔を赤らめて言った。
「きれいごと言うなよ。自分が捨てたんじゃないか」
堰を切ったようなその声はかなり声高だった。店の客数人が孝太に視線を浴びせ
た。
「すまん」父は小声で言った。
客の目が『あれは別れた親子の面会なのだろう』と囁いているように感じられ孝
太は恥ずかしかった。
「父さん・・・。俺、来年高校受験だし。だからもう会えないかも知れない」
孝太はぼそっと言った。
「悪かった。今言ったのが気に障(さわ)ったのか」
「そうじゃないよ。父さんに会う日、母さんがへんに優しいんだ」
「そうか。孝太は優しい子だからなあ」
そう言ったきり父は何も言わなかった。
「父さん。ここの天ぷらおいしいよ」
孝太はとってつけたように言った。
見上げると父の目が赤いのが見えた。まずいことを言ったな、と孝太は思った。更
に無言になった二人は、店内のテレビの音を所在なく聞いていた。父の髪に白いも
のがあった。孝太は無性に父がかわいそうに思えてきた。
「そうだ父さん。春になったら釣りにいかない?」
「うん?いいのかい?」
「受験、余裕があるんだ。父さん、数学が好きだったよね。僕も数学、できるんだ。
やっぱり親子だね」
そう言って孝太は残っていたエビフライを「バッチグウウ」とおどけて頬張ると、
何故か涙が止めどなく流れ出るのだった。