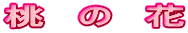
古ぼけた辞書の間から、触れると壊れてしまいそうな押し花が出てきた。色がすっかり変色していて、紙に近い状態に見えた。
ふと、少女の頃、家の庭に咲いていた桃の花びらを本の間に挟んで押し花にしたことを思い出した。あの時の、秘密を閉じ込めた
あの気持ちが鮮明に甦ってきた。
家から一里(4キロメートル)ほど離れた所に小学校があった。川と山の間をくねるように国道が続き、学校までは歩いて通ったも
のだった。季節の変化は山からも川からも目に入るが、一つ一つに感動するのでなく、むしろ、それが当たり前に思えていた。
春は川にそって迂回している道路づたいに白く房状にニセアカシアが咲き、その香りは遠くからでも知ることが出来た。山側の
土手には、ホタルブクロが咲き木苺が実り、特に雨上がりの枝葉に見つける木苺は、美しい宝石のようで、熟している木苺に強
く触れるとはらっと地面に落ちてしまうのである。採るときのその緊張感は木苺の形と色彩の美しさへの少女の憧憬であったかも
しれない。
早朝は朝霧が巻き、人家も川も山も乳白色に包まれ子供達は影絵のようにその中を学校に通った。冬の朝の吐く息は真っ
白で、その寒さは足のつま先が痛く感じるられるほどになるが、そんな中でも遊びをさがすのが子供達である。道路の水溜り
の凍っている所を見つけては我も我もと助走をつけてから滑ったり、川からかなり高い所を走る道路の川沿いの端に四十センチ
間隔に置かれている石の上を牛若丸ごとくにひらりと跳び進むのである。とても危険なことであるが、不思議に真下の深い川に
落ちた子供の話は一度も聞かなかった。川の中には水に逆らうように大きな岩が点在していて、そのあたりをキセキレイが尻尾
をピンピンと上下に跳ねて澄んだ空気を啄ばむように群れている様は一枚の絵画ようであった。
人々は戦後の貧しさから、生きる活気を時代に求めて行っただろうが、山里の子供達は日々を過ごすことで夢中だった。
Iちゃんと私はいつも学校帰りが一緒だった。Iちゃんは九人兄弟姉妹の四番目であったため、妹や弟の世話をするお姉さんで
あったから、学校の帰り道はIちゃんが一番自由にいられる時であった。二人は舗装されていない道路を砂煙あげて走り去るトラ
ックの通り過ぎるのを、目をつぶって鼻、口を押さえて砂煙のおさまるのを待った。雨の時などは、水溜りに落ちた車のガソリン
が水に浮いて虹のように見えるから、二人で靴を浮かして靴裏でかすかに触っては、油の色彩の輪を動かすことを楽しんだ。
道中は長い長い道草の連続なのである。
あの日、Iちゃんは買ってもらったばかりの白い鞠(まり)をお母さんに作ってもらった布袋に大切そうに入れて持ち帰っていた。
そのころ、学校の休み時間に
一匁の一の介さん一の字が嫌いで
一万一千一千億一斗一斗一斗豆お倉におさめて
二匁に渡した オーランショ
と毬つきをして遊ぶことがはやっていた。Iちゃんは毬つきがとても上手だったが、今までは、友達のものを借りての毬つきだった
けれど、今日から自分の毬があるから嬉しそうだった。その日、川沿いの道路脇に川を見下ろすように桃の花が咲いていた。
Iちゃんは「きれいだから、桃の花採ろうよ」といった。
私は高い所から見下ろすと眼下に深い川底が見えて、とても怖くて
「怖いよ」と私は最初から諦めることを言った。
普段から木登りの名人なIちゃんは諦めなかった。細い枝に足をかけて、枝を一つまた一つと折った。得意げで楽しそうだった。
くるりと振り返って戻ろうとしたとき、枝に引っかったたのか大切な毬の入った袋を川に落としてしまたのである。Iちゃんは「毬が、
毬が」と言って川の波にもまれて流れて行く毬を追いかけて走り出したのである。私はIちゃんが道に放り投げて行った桃の花
を取り上げるとIちゃんの後を追った。この先に道路から川原に下りられる細道がある。そこは川幅が広く、大きく迂回しているし
中瀬があり、深い流れは向こう岸に行ってしまうから、そこまで走ろうと思った。Iちゃんも同様に思ったらしく、走りに走って行っ
た。後姿は何かに怒っているように見えた。細道を転がるように下りて、鞠へ一直線に進んで行くようにバチャバチャ川に駆け
込んでいった。流れに足をすくわれて転び、起きあがると又苔むした石に滑って転び、ずぶぬれのIちゃんは、それでも必死に
毬を追った。水はIちゃんの胸元くらいまでもあり、私はIちゃんが流されてしまうのではないかと
「Iちゃん、Iちゃん、Iちゃん」と涙声で叫び続けた。
流れていく毬を目で追いながらもどうすることもできなかった。全身びっしょり濡れたIちゃんは精も根も尽きた顔で岸辺に上が
ってきた。このとき、私は泣いていたがIちゃんは泣いていなかった。
二人は無言で川原から細道を登って道路に出た。Iちゃんが採った桃の花を黙って私は差し出した。今まで泣いていなかった
Iちゃんが突然泣き出した。Iちゃんは体も心も濡れてしまった声で泣いていた。
貧しい中で、やっと買ってもらった毬を失った悲しみと、自分に怒っている様子のIちゃんの哀しみが伝わり、歩きながら私まで
もまた泣けてきた。歩く度に揺れるIちゃんの掌にある桃の花が何か悲しかった。
Iちゃんとの出来事は誰にも話さず、年月は過ぎてしまったが、白い毬を拾い上げようとしゃにむに川に入って行ったIちゃんの後
姿が今でも私の心の奥に桃の花とともに思い出となって残されている。
